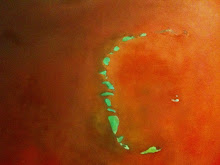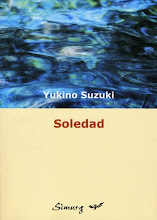リマの友だちの家はオリーブの公園の中にある。500年前にスペイン人たちが植えたものだ。幹が太く、木面はぼこぼこ、そんな老木が何百本もずっしりと根を張っている。気候は夏以外は低温多湿で身体の芯まで冷え切ってしまう。ブエノス・アイレスよりも緯度的にはずい分北なので温かいのかと思っていたら、まだ冬のような冷え込みだった。
空からの眺めでは、アンデス山脈を越えた先はどこまでも白い雲に覆われ、なにも見えなかった。リマはその雲の下にあった。500年ものあいだこの気候のもとでよく育ったものだと思う。オリーブといえば地中海のからっとした天気を思い出すからだ。それにしても、この木たちは、コンキスタドールがここにやって来てからのことをすべて見ていたことになる。できることなら話が聞きたいものだ。
10月はSeñor de los Milagros (奇蹟の主) の月だった。伝説の奇蹟のキリスト像(かつて大地震が起きたとき、この像のある壁だけは決して崩れなかった)を担いて街を行進する。リマの中心は紫色の垂幕、看板で埋まり、外国からも続々と行進に参加すべくカトリック信者が集まる。熱心な信者は紫色(Morado)に身を纏い一ヶ月を過ごすのだという。
27日は交通の混雑が懸念されたので早朝から市内観光をすることにした。像が置いてあるリマ中心部のナザレノ教会では朝のミサが厳かに執り行われていた。そして、教会の周辺では、この行事につきもののお菓子Turrón がいたるところで売られていた。
 街にはアジア的なカオスがある。運転マナーはないに等しく、歩いているかのごとく車を前に進めるのがペルー式。前に障害物があれば空いているところを探す。かといって危険かというとそうでもなく、荒っぽさは感じられない。このカオスを見ていて思ったのだが、ペルーのひとびと、山から下りてきたひとびとは、鳥のような感覚を持っているのではなかろうか。高山では平面、直線などないのだから。
街にはアジア的なカオスがある。運転マナーはないに等しく、歩いているかのごとく車を前に進めるのがペルー式。前に障害物があれば空いているところを探す。かといって危険かというとそうでもなく、荒っぽさは感じられない。このカオスを見ていて思ったのだが、ペルーのひとびと、山から下りてきたひとびとは、鳥のような感覚を持っているのではなかろうか。高山では平面、直線などないのだから。 面白いのはタクシーだった。メータがないので乗る前に運転手と値段交渉しなければならない。はじめて利用する観光客など相場がわからないひとはどうするのだろう。
先月、友だちがペルーからブエノスに遊びに来たとき、骨董品収集が趣味で、ありとあらゆる装飾品をこよなく愛する彼女が、旅行鞄の中に見たこともないような果物やお茶、木の実などを詰めてやって来たのを見て驚いた。その果物を割ってカエルの卵のような実をむさぼっているのだ。ペルーのなにかが彼女を変えてしまった。それからというもの、わたしにはペルーという国がマジカルなものに思えてならなかった。
桟橋の上に設えられたRosa Nautica という店で魚介類を満喫した。新鮮な魚が豊富に採れるということは海鳥の多さからも十分にうかがえる。海は相変わらず曇り空の下で暗い色をしている。窓際の手摺に一羽のカモメがとまった。店のひとに尋ねると、この鳥はいつもここに飛んでくるらしく、みんなにMilagro(奇蹟)と呼ばれているとのこと。
海岸通りは石がぎっしり積み重なった崖の下にあり、大地震が起きたら間違いなく崩れそうなのだが、その上には観光客を迎えるための高層ホテルがずらりと並んでいる。ここも、世界のどこにもあるようないわゆる海沿いの観光地の風景になっていくのだろうか。大地震が起こらない限り、きっとそうなのだろう。でも、もし、起こったら、彼らはきっと、また奇蹟の主を信じ、鳥のように生きていくのだろう。彼らは、蘇らないものには関心がないのだ。この大地は、形のあるものを崩し、永遠の回帰を彼らに教えてきたのだろう。
海岸通りは石がぎっしり積み重なった崖の下にあり、大地震が起きたら間違いなく崩れそうなのだが、その上には観光客を迎えるための高層ホテルがずらりと並んでいる。ここも、世界のどこにもあるようないわゆる海沿いの観光地の風景になっていくのだろうか。大地震が起こらない限り、きっとそうなのだろう。でも、もし、起こったら、彼らはきっと、また奇蹟の主を信じ、鳥のように生きていくのだろう。彼らは、蘇らないものには関心がないのだ。この大地は、形のあるものを崩し、永遠の回帰を彼らに教えてきたのだろう。