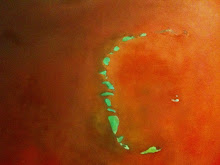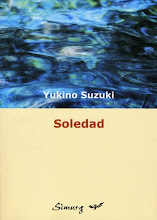2010/06/29
WAKA WAKA 2010
2010年のW杯はどういうわけか密着している。これまではW杯があっても、いつ、どこで開催されているかすら知らなかったし、まったく興味がなかった。この変わりようはいったいなぜか。
そのきっかけとなったのは、甥っ子DanieleのFacebookへの書き込み。それが琴線に触れた。
La storia sta per essere scritta. いま歴史がはじまろうとしている。
Oggi è il giorno dei Mondiali di Calcio. 今日からW杯がはじまる。
Per la prima volta in Africa. アフリカで、はじめて。
L'Uomo è nato lì ma, per tanto tempo, l'uomo stesso non ha consentito all'Africa di mostrare i suoi veri colori. 人類が誕生した土地であるにも関わらず、人類はその大地の本当の色を隠し続けていた。
Ora quel momento è arrivato. いま、そのときが来た。
Lo Sport e la Musica uniscono. スポーツと音楽がひとつになる。
"The Waiting is Over." もう待つ必要はない。
"It's in Your Hands"... きみたちの手のなかにある。
"Now it's time for Africa". アフリカの時代がやってきた。
と、こんな具合。その後、開幕式を観て、試合を観ているうちに、なんだか凄く面白いことが起こっているような気がして、ずんずんのめり込んでいった。南米では国技と呼ばれるほどサッカーは国民のメンタル部分で重要な位置を占めている。巨人ファンの兄が、巨人が負けると不機嫌になったり、中日ファンの母が中日が不調だとじぶんも元気がなくなるように、スポーツというのは集合無意識を呼び覚ます。最初に観戦していて思い出したのはローマのコロッセオの闘技。もちろん生でみたことはないので映画のワンシーンなど。じぶんのなかの野生も刺激するような気がした。これは、わたしたちの根源的な部分に訴える、地球上の民族の祭典だ。以来、友だちの戦術分析を参考にしながらひたすら観戦し続けている。
ちなみに、アルゼンチンでは、サッカーの放映は、公共チャンネルでメインの試合(視聴率が高そうな方)の生中継、それと同時に、ケーブルでもうひとつの試合が流され、もうふたつくらいは、常時、サッカー関係の分析や討論会、インタビューをやっている。南米ではサッカーの話題に事欠かないというのもあるだろう。とにかく、最近は朝から晩までそれだけで終わっている。毎日の生活がサッカー一色になるなんて!
ところで、今回の日本帰国では気になったことがあった。現在の日本の若者は外国に関心を持っていないということだ。携帯とパソコンと仲間内のつきあいが楽しみで、外国のことにはまったく関心がないし知らない。知らなくてもいい。ネットでなんでもわかる時代だし、見たい景色も津々浦々いつでも簡単に拾い出すことができる。実際に労力・体力を使ってそこへ行きたいとも思わない。翻訳機械や辞書が普及して、覚えることは機械がやってくれる。脳みそを手の平に持ってじぶんは空っぽになる。と、そこまではいかないにしろ、なんだかちょっと寂しいと思った。
街頭インタビューの「外国に住みたいですか?」という質問に「トイレとか汚そうだから嫌だ」、「食べものがまずそう」と答えている若者もいた。マラドーナが南アフリカのトイレ事情に困り、選手全員のために日本からウォッシュレットを取り寄せさせたというエピソードがあった。それ以来、南アフリカのお金持ちはウォッシュレットがブームなのだそう。あまりのタイムリーさに笑ってしまった。
ユニクロの社内用語が英語になった。今後は日本から外国へ市場を拡大するという話。だいたい、ひとつの言語でまかなっているという状態は現在の世界のなかでは珍しいケースらしく、アフリカや欧州など数ヶ国語ができてあたりまえの世界なのだ(西江雅之の『「ことば」の課外授業』)。わたしは、ユニクロの選択がおかしいとは思わない。市場主義に走っているという感じはなきにしもあらずだが、それじゃあ、これから、どうするの?という単純な疑問も湧いてくるはず。日本のよいものを外国に紹介していくことが、どうして悪いのだろうとわたしは思うのだけれど。
ふたつ、みっつの言語を使うことは、そのひとの生まれ育った文化を捨てることではないし、だいたい、じぶんを振り返ってみても、わたしのどこからどこまでが日本文化でどこからどこまでがイタリア、アルゼンチンなのか、首から上が日本で、指先がイタリアで、足の裏がアルゼンチン?わたしは、ひとりのひととして、固有の文化を生きている。
渋谷の交差点でサムライブルーに熱狂し、お祭り騒ぎをした若者たちを見て少し救われた。日本のあちこちでみんながこの勇敢な戦士(というと語弊があるかも知れないけれど)たちにチューニングしていると思うと嬉しい。
これは、アルゼンチンでも同じように感じることだし、イタリアでも同じこと。わたしのなかに共存する文化がそれに同調している。
登録:
投稿 (Atom)