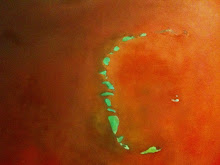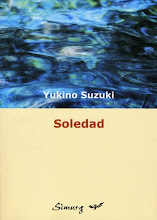昨日は、アルゼンチン在住20年という日本人女性と、ブエノスの日本庭園でお会いした。そもそも彼女との出会いは、日本人社会とはまったく無縁の、去年の9月の展示会のとき。わたしは上の階で絵の展示、彼女は下の階で広島原爆平和のための折鶴展をしていた。
一ヶ月のあいだ、上の階の自分の展示場に行くのに、毎日その折鶴の会場を通っていたので、彼女には何度も会った。けれども、あまり話をする機会がなくて、その後Twitterで、どういういきさつだったかまったく覚えていないけれど、言葉を交わすようになり、彼女のアルゼンチン在住20周年を記念してお茶でもしませんかということになった。20年前に青年海外協力隊からここに派遣されてきた草分け的存在。なにごとも勉強と前向きに飛び込んでいく姿勢には打たれる。
 昨日のブエノスはお天気も良く、日本庭園はすごい人出。相変わらず、園内は綺麗に清掃整備がゆき届き、ブエノスに突如現れた別世界といった感じ。その異次元的空間では、みんな朗らかで親切、ちょっと日本みたいでほっとする。
昨日のブエノスはお天気も良く、日本庭園はすごい人出。相変わらず、園内は綺麗に清掃整備がゆき届き、ブエノスに突如現れた別世界といった感じ。その異次元的空間では、みんな朗らかで親切、ちょっと日本みたいでほっとする。 庭園を散歩していると、ひとりの日本人の男子が現れた。WASEDAのロゴ入りのポロを着ていたが、卒業旅行で南米をバックパックの一人旅中。欧州と南米とどちらにしようか迷ったが南米を選んだのだという。ちょうど昨日は岡本太郎の生誕百周年、「迷ったときは難しい方を選べ」という太郎の言葉を思い出した。すると、WASEDAボーイは、選べること自体が幸せだと思うと言った。岡本太郎の記念日に相応しい出会いである。
そのまま、みんなで連れ立って園内の図書室に行き、そこの係員と話しているうちに、書道の話題になった。みると、室内にも書がいくつか飾ってある。にわか書道屋のBiBi太郎も書道には関心がある。すると、そのWASEDAボーイこそが、実は、四段の達人だということがわかり、それじゃあここで一筆書いてみないかと、たちまちデモンストレーションすることになった。
筆と墨汁と紙が準備されると、「座右の銘を書きます」とすぐに書くものも決まって、四段が取りかかる。呼び込み係はわたくしBiBi太郎。すぐに、なんだなんだとひとが集まってきた。WASEDAボーイは緊張することもなく、「日々是好日」とささっと書いていった。その意味をスペイン語で説明すると、みんなが感動した。そして、観客と記念撮影。彼にとってもよい思い出になったことだろう。書は図書室に残るし、いつか飾ってもらえるかも知れない。リクエストに答えてもうひとつ、絆という字も書いてくれた。
 このWASEDAボーイ、大学ではサッカーをしていたのだとか。スポーツマンである。一昨日はブエノスの公園で子どもたちとサッカーをして遊び、真面目でやさしく、礼儀正しいニッポン男児は、たちまちアイドル的存在となり、翌日はさっそくパーティに招待されたのだとか。サッカーに国境はない。言葉もいらないのだろう。
このWASEDAボーイ、大学ではサッカーをしていたのだとか。スポーツマンである。一昨日はブエノスの公園で子どもたちとサッカーをして遊び、真面目でやさしく、礼儀正しいニッポン男児は、たちまちアイドル的存在となり、翌日はさっそくパーティに招待されたのだとか。サッカーに国境はない。言葉もいらないのだろう。日本庭園の売店で、三人で鯛焼きアイスをいただきながら、しばし南米の日本を満喫した。移民の方々の汗と努力によっていま、ここがあるということを、日本だけでなくどの国のひとも感じているのがアルゼンチン。WASEDAボーイはそんな多国籍共存のなかで育つ子どもたちを見て、いいなあ、とつぶやいた。